「風の時代」という言葉を最近よく耳にしませんか?占星術の世界では、2020年12月から私たちは新しい時代に入ったとされています。これまでの物質重視の価値観から、より精神的で自由な生き方へと意識がシフトしているのです。
そんな現代に、なぜ700年も前に書かれた『徒然草』が注目されているのでしょうか?実は、作者の吉田兼好の生き方や思想には、風の時代の価値観と驚くほど共通する要素があるのです。古典を読むのは難しそう…と思われるかもしれませんが、きっとあなたの人生観を豊かにしてくれるはずです。
風の時代ってどんな時代?
まずは風の時代について簡単におさらいしてみましょう。占星術では、約200年ごとに時代の特徴が変わるとされており、これまでは「地の時代」でした。地の時代は物質的な豊かさや安定、組織への所属などが重視される時代でした。
しかし2020年12月から始まった「風の時代」では、価値観が大きく変化しています。
風の時代の5つの特徴
- 軽やかさ:重いものより軽いもの、所有より体験を重視
- つながり:物理的距離を超えた心のつながりを大切にする
- 個性:画一的でなく、一人ひとりの個性を尊重する
- 精神性:物質的満足より心の豊かさを求める
- 自由:固定された枠組みより流動的な生き方を選ぶ
リモートワークが普及し、副業が当たり前になり、SNSで世界中の人とつながれる現代は、まさに風の時代の特徴を体現していますよね。でも実は、こうした価値観を700年前に実践していた人がいたのです。それが吉田兼好でした。
時代の先駆者・吉田兼好という人
興味深いことに、占星術では前回の風の時代は鎌倉時代だったとされています。つまり、吉田兼好が生きた時代そのものが風の時代だったのです。
吉田兼好(本名:卜部兼好)は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて生きた人物です。もともとは朝廷に仕える官人でしたが、30歳頃に突然出家し、世俗を離れた自由な生活を送るようになりました。
当時の常識では考えられない選択でした。安定した地位を捨て、組織に属さず、一人で思索にふける生活を選んだのです。これはまさに現代でいう「会社を辞めてフリーランスになる」ような、勇気ある決断でした。
兼好は京都の郊外で質素に暮らしながら、日々感じたことや考えたことを自由に書き留めました。それが『徒然草』として後世に残されています。特定の読者や目的を意識せず、ただ「つれづれなるままに」心の赴くままに書いた文章は、現代のブログやSNSの投稿にも似ています。
『徒然草』に見る風の時代の生き方
では具体的に、『徒然草』のどんな部分が風の時代と共通しているのでしょうか?
執着を手放す智慧
兼好は物質的な豊かさへの執着を手放すことの大切さを説いています。「世の人の心まどはすこと、色欲には如かず。人の心はことにふれて移りやすきものなれど、中にも色に触れてうつろひぬれば、正しきついでも忘れて、かたくななる心づかひしたり」
現代風に言えば、「物やお金に執着しすぎると、本当に大切なものを見失ってしまう」ということです。風の時代の「所有より体験」という価値観と完全に一致していますね。
変化を楽しむ美意識
『徒然草』で最も有名な一節の一つが「花は盛りに、月は隈なきをのみ見るものかは」です。これは「桜は満開の時だけ、月は満月の時だけを見るものだろうか?」という意味で、不完全や変化の中にこそ本当の美があることを教えています。
完璧を求めるのではなく、移ろいや変化を受け入れ、楽しむ。これは風の時代の「流動性」を重視する価値観そのものです。現代でも、完璧なインスタ映えより、自然体の日常を大切にする人が増えていますよね。
多様性を受け入れる寛容さ
兼好は『徒然草』の中で、貴族から庶民まで様々な立場の人々を描いています。時には批判的な目線もありますが、基本的には「いろんな人がいて、いろんな生き方があるものだ」という温かい視点で人間を観察しています。
「人はおのおの思ふところあり」という言葉からも分かるように、一人ひとりの考えや生き方の違いを自然なこととして受け入れています。これは風の時代の「個性の尊重」「多様性の受容」という価値観と重なります。
内面の声を大切にする姿勢
兼好は外的な権威や世間の常識よりも、自分の内面の声に従って生きることの大切さを示しています。出家という選択も、世間体より自分の心の声に従った結果でした。
「心の師とはなれ、心を師とせざれ」という言葉もあります。これは「自分の心をよく観察して師とせよ、しかし感情に振り回されるな」という意味で、現代のマインドフルネスや瞑想の考え方とも通じています。
軽やかな人間関係
兼好は人間関係についても独特の視点を持っていました。「交わりあさく、恨みなき時は、なほ心やすし」つまり、深く執着しすぎない軽やかな関係こそが心地よいということです。
これは現代のSNSでのつながりにも通じる考え方ですね。無理に深い関係を築こうとせず、自然で心地よい距離感を保つ。風の時代の「つながり」の本質を表しています。
現代に活かせる兼好の教え
兼好の教えは、現代の私たちの生活にも直接応用できます。
SNSで他人と比較して落ち込むときは、兼好の「人はそれぞれ」という寛容な視点を思い出してみてください。キャリアに迷ったときは、外的な評価より内面の声に耳を傾ける兼好の姿勢が参考になります。
変化の激しい現代だからこそ、兼好の「変化を楽しむ」美意識は心の支えになるでしょう。完璧を求めすぎず、今この瞬間の不完全な美しさを味わう。そんな生き方が、風の時代には特に求められているのです。
まとめ
『徒然草』は単なる古典文学ではありません。700年の時を超えて、風の時代を生きる私たちに深い智慧を授けてくれる人生の指南書なのです。兼好法師の自由で軽やかな生き方から、現代を豊かに生きるヒントを見つけてみませんか?
ぜひ一度、『徒然草』を手に取ってみてください。きっと風の時代の新しい価値観が、あなたの中でも芽生えてくるはずです。

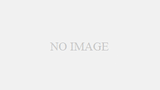
コメント